1. 日常からできる防災対策を解説
日本は地震大国として知られ、地震に台風、大雨に洪水など災害が頻繁に発生します。日本は特有の地理的条件から災害時に復興活動に時間を要する地方が存在しています。「能登半島」山が多く、海に長く突き出した地形によって交通アクセスが難しく、災害時には復興に時間を要する地域となっております。
防災対策の方法について災害に対してどのような備えをし、防災対応するか、すぐできる防災セルフチェックなど役立つ情報を提供します。
2. 防災の基本対策
①3つの防災対策セルフチェック
地震対策の基本は、まず自宅の耐震性を確認することをオススメします。持ち家か賃貸であっても簡単に自己診断をすることができます。
(1)昭和56年(1981年)6月1日以降に建てられた物件か
これは旧耐震の物件か、新耐震基準の建物かを診断できるためです。旧耐震構造でも補強の柱が入っているかなどでも倒壊に大きく影響します。
(2) 傷んだ箇所はない。ひび割れなど痛んだところはその都度補修している(されている)
傷んだ箇所がある場合、大きな地震があった際大きな被害に直結してしまう可能性があります。

(3)建物の形はほぼ長方形、複雑な形ではない
建物が複雑な造りだったりするとそれを支える支柱も複数必要となり、耐震性にも影響を及ぼします。
(4)セルフチェックのまとめ
以上が(1)〜(3)は簡単にセルフチェックできる方法です。
気になる点が一つでもあった方は耐震性を調べてみたい方は全国各地に診断士が在籍していますので自分の住まいの近場で診断士がいてるか調べてみるのをオススメします。
地方自治体によっては耐震性診断の費用を100%補助をされ、耐震補強工事にかかる費用の補助金も一部負担くれる自治区も存在します。
コレクトボイスでは古くなった古民家の再生も携わっていますので、耐震に関するご相談やお悩みを聞いてみたいという方は以下お問い合わせフォームよりご相談ください。
②災害に対する日常的な備え
もしもの時の備えをしておく事も重要です。災害時に確保したいのは最低限の生活インフラです。水、電源は必要最低限で必須となります。スマートフォンがあれば最低限家族や身内と連絡をし、身の安全の確認、緊急連絡もできるので、2000Wh程度のポータブル電源を備えておくと命綱となる事もあります。
ポータブル電源は一度充電しておけばかなりの日数電源が確保されます。多少放電はするものの災害時には十分活用出来るので購入後満タン充電をし備えをしておきましょう。
防災用のグッズや非常食等を買っておき、すぐに取り出して動けるところに保管しておきましょう。防災グッズ一式のリュックとポータブル電源をひとまとめに備えておくと慌てずに行動できます。
ネットショップでは防災に必要なグッズがまとめてくれた必需品を一つ用意していると安心です。
非常時を想定して家族で避難計画を立て、防災訓練で想定しておきましょう。また、就寝時による被災は非常に厄介です。能登半島地震による死者の要因の大半は圧死によるものです。寝室は必ず家具の固定を行い、出口の確保、非常用リュックの準備を講じておきましょう
③災害時の地域コミュニティの役割
地域コミュニティの連携も防災にきっと役立つ事でしょう。防災訓練や情報共有を行うことで、防災意識を高めることができます。
ま地域コミュニティと地域団体、民間団体は重要な役割を担います。被災地の復興には迅速にかつスピード感を持った活動には欠かせん。政府からの支援と合わせて官民連携を行なっていくことが現実的な復興活動といえます。
3. 災害発生時の防災対応
次に災害が起きた時どの様に動いていくべきかを解説していきます。
①初動対応(自分のいる場所を確認)
地震が起きた時の発生場所によって、行動すべき内容が異なってきます。
身の安全を確保することを優先させて、机の下に隠れ頭を保護するとしています。
しかし地震発生時に、学校などの避難場所地域と指定されている場所だとは限りません。古くなっている一軒家の場合も考えられます。
その様な場合、建物の倒壊とガス管破裂等を優先に危惧されます。
まず身の安全を確保することが最優先させます。机の下に隠れたり、頭を保護したりして、揺れが収まるまで安全な場所に留まります。
屋外の場合、落下物に注意して建物には近づかないようにしましょう。
②出口の確保
揺れが収まったら、すぐ避難ができるように窓やドアを開けて出口の確保をします。
避難時は必要最低限の物を携帯し、足を守るために靴を履きましょう。出口の左右を確認してから出る様にし、慌てて外に飛び出さないよう注意してください。
③火の元のチェック
地震発生時にもし火を使っていた場合は、慌てず速やかに消します。
ガスの元栓を締め、電気機器は電源プラグを抜きます。電源復旧時の電気火災にならないようブレーカーを落とし、二次被害を防ぎましょう。

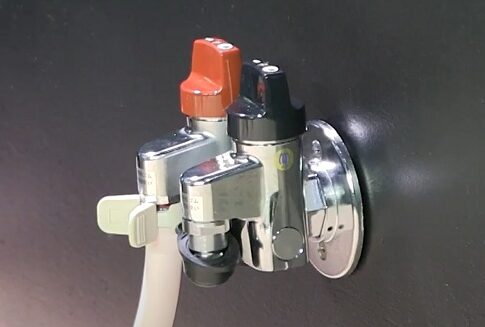
④周囲の救護と安否確認
自身の安全確保をしたのち、周囲の救援、救護を行います。高齢者や要配慮者がいる家庭には積極的に声かけをしましょう。
4. 能登半島地震について
能登半島地震の当時の状況、今後の対策と私たちが出来ることについて見ていきます。
①能登半島地震の当時の状況
能登半島は石川県北部に位置し、日本海に突き出た半島です。美しい自然景観や歴史的な文化遺産が豊富で、観光地としても人気があります。しかし、その地理的特徴から地震や津波のリスクが高い地域でもあります。
地震が発生した際、震度計による揺れ感知を通信障害によってデータを送ることができず、半月以上経ったのち輪島市と能登町の震度が震度7と震度6強と判明しました。
金沢大学地震学の平松良浩教授によると、マグニチュードが大きく、長い断層が複数見られる能登半島では今回の地震によって新たに隠れていた断層が刺激され、引き続き大規模な地震が起きる可能性があると指摘しています。
②能登半島の壊滅状況
能登半島は複数の活断層が存在し、過去にも大規模な地震が発生しています。下の写真は2024年1月1日能登半島地震前と直後の航空写真です。比較してみると、家の軒並みがほとんどなくなってしまっている事がわかります。

上から撮影した航空写真でみても相当な被害状況であるとみてとれます。
③能登の災害対策と今後の課題
このような背景から、能登半島では入り組んだ地形が問題ということがわかります。まずは復興支援を優先させて、日常的な防災意識を高めつつ、自分たちが出来ることを対策していくべきだといえます。
5. まとめ
地震災害に備えるには、日頃から適切な防災対策を行い、災害発生時に冷静に適切な行動が取れるよう事前に基本的な知識を知っておくことが大事です。そして地震対策は事前に備えることが出来ます。何が起こっても焦らず適切に対応することが求められますので、この記事を読んで頂いた方は気になる項目があったならチェックをし、今できる備えを始めましょう。


コメント